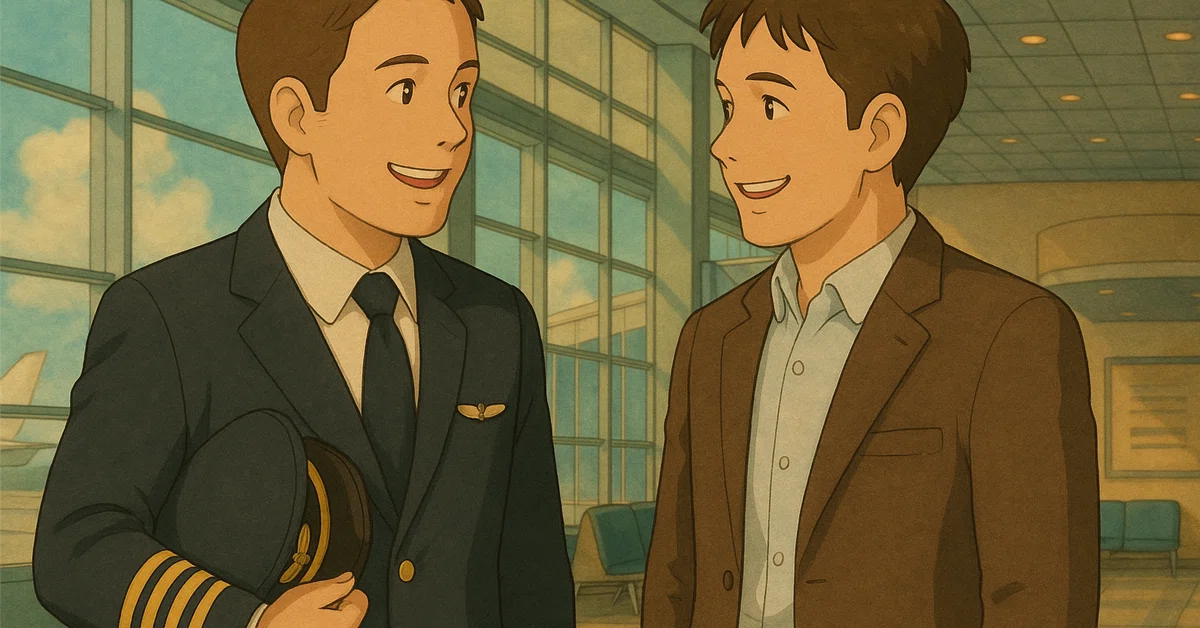「Make Room」に込められたアメリカの本音——パーソナルスペースから読み解く日米文化の距離感
旅先での何気ないひとことが、その国の文化の核心を突いてくることがある。私がアメリカで体験した「Make Room」という言葉も、まさにそうだった。
ある日、私は現地のビュッフェレストランに立ち寄った。日本でいう「バイキング」スタイルの、いわゆるセルフサービスの食べ放題。アメリカではこれを「Buffet(バフェイ)」と発音する。お腹を空かせて意気揚々と料理を取りに向かうと、人気料理の前にはずらりと行列ができていた。
私もその列に並び、無意識のうちに前のアメリカ人との距離を日本的感覚で“詰めて”立っていた。そう、これがきっかけだった。
前のアメリカ人男性がふと振り返り、こう言ったのだ。
「Make Room.」
一瞬、頭の中で直訳が浮かぶ。「部屋を作れ」?…は? 何のことだ?ここはレストランのフロア、部屋も何もないじゃないか。
だが、すぐに気づいた。Room には「部屋」以外に「空間」「スペース」という意味がある。つまり、「もっとスペースを空けて並んでくれ」ということだったのだ。
この一言をきっかけに、私はアメリカ人と日本人の「距離感」に対する認識の違いに深く興味を持つようになった。
文化に根ざす「距離感」:パーソナルスペースという概念
人は誰しも、自分の周囲に「見えないバリア」を持っている。それが「パーソナルスペース(Personal Space)」だ。
これは、他人に近づかれると不快に感じる、心理的・物理的な距離のこと。人によって、また文化によってこの“快適な距離”には大きな差がある。
日本人は、世界的に見てもこのパーソナルスペースが狭いと言われている。満員電車に詰め込まれても、駅のエスカレーターで一列に並んでも、比較的ストレスに耐えるように訓練されてきている。一方で、アメリカ人はパーソナルスペースが非常に広い。挨拶ひとつとっても、2〜3歩の距離を取って「Hi!」と声をかけるのが一般的だ。
つまり、アメリカ人から見れば、日本人の“詰めて並ぶ”習慣は、**「押し付けがましい」「不快に感じる」**可能性があるのだ。
「Make Room」に含まれる無言のメッセージ
あの時の「Make Room」という言葉には、ただ物理的に“下がれ”という以上の意味が含まれていたように思う。おそらく彼の中には、「なぜこんなに近くに立つんだ?」「俺のスペースを侵すなよ」という軽い苛立ちすらあったかもしれない。
日本では「少しでも後ろの人を早く料理に近づけよう」とか、「並んでいるのに間が空いていたらマナー違反」とさえ思われることもある。だからこそ、日本の感覚で“間隔を詰める”のはごく自然な行動だった。
しかし、アメリカでは真逆。「間を空ける」ことが礼儀であり、気遣いなのだ。つまり、空間を保つことで相手のパーソナルスペースを尊重していると解釈される。
私が無意識に“近づいた”ことで、相手のテリトリーを侵してしまった——それが「Make Room」の真意だったのだろう。
なぜ日本人は“詰める”のか?
では、なぜ日本人はスペースを詰めがちなのか。それには、歴史的・社会的背景が関係している。
まず、日本は物理的に“狭い国”だ。国土面積はアメリカの約25分の1。特に都市部では、通勤電車に人がギュウギュウに詰め込まれ、飲食店も席と席の間が狭いのが当たり前だ。日常的に“他人との距離が近い”環境に慣れている。
さらに、日本社会は**“集団での秩序”を重んじる文化がある。列に並ぶときも、「間を空けすぎると列が乱れる」「割り込みだと思われる」といった心理が働く。「周囲に迷惑をかけないように」とする意識が、“間隔を詰める”という行動に繋がる**。
つまり、日本では「距離を詰める=協調・配慮」の表れであり、アメリカでは「距離を空ける=配慮」になる。この真逆の価値観が、「Make Room」という一言を生んだのだ。
海外で気をつけたい、日本人の“距離感”
この出来事以降、私はアメリカで行列に並ぶとき、前の人との間に“1メートルくらい”のスペースを確保するように心がけるようになった。最初は少し違和感があったが、慣れてくるとそれがむしろ快適に感じるようになった。
逆に、日本に帰ってきてから「間隔を空けすぎてるよ」と注意されたこともある。駅の券売機で“欧米間隔”を取っていたら、後ろの人に「あの、並んでますか?」と声をかけられたのだ(笑)。
文化が違えば、距離感も変わる。だからこそ、その国の“適切な距離”を知ることは、異文化コミュニケーションの第一歩なのだと思う。
「縄張り意識」としてのテリトリー
人間にも「縄張り(テリトリー)」という本能的な感覚があると言われている。
動物が自分の領域をマーキングするように、人間も「ここからここまでは自分の空間」と無意識のうちに線を引いている。カフェで隣に誰かが座るとき、やたら近くに座られると居心地が悪く感じたり、電車でわざわざひとつ席を空けて座ったりするのも、まさにその表れだ。
面白いのは、その“縄張りの広さ”も文化によって異なること。広大な土地で育ったアメリカ人は、当然その縄張りも広い。一方、日本のように限られたスペースで生活していると、縄張りも自然とコンパクトになる。
だから、日本の“ぎゅうぎゅう文化”を当たり前にして育った私が、アメリカで“アグレッシブな近さ”になってしまったのは、ある意味当然のことだったのかもしれない。
おわりに:「Make Room」は単なる命令じゃない
「Make Room」という言葉をただの命令として受け取っていたら、私はその場で少しムッとしていたかもしれない。
でも、文化の背景を知れば知るほど、それは相手からの「距離を尊重してくれ」というサインであり、むしろ丁寧なコミュニケーションの一部だったのだと今では思える。
異文化を旅するというのは、言語だけでなく、「空気」や「距離」や「沈黙」さえも学び直すことだ。
そして、そんな小さな出来事の中にこそ、私たちが普段気づかない“当たり前”が隠されている。
日本とアメリカ。その文化の違いを一言で言うなら、「Make Room」。
それはただのスペースの話ではなく、人と人との間に必要な“心のゆとり”の話でもあるのかもしれない。