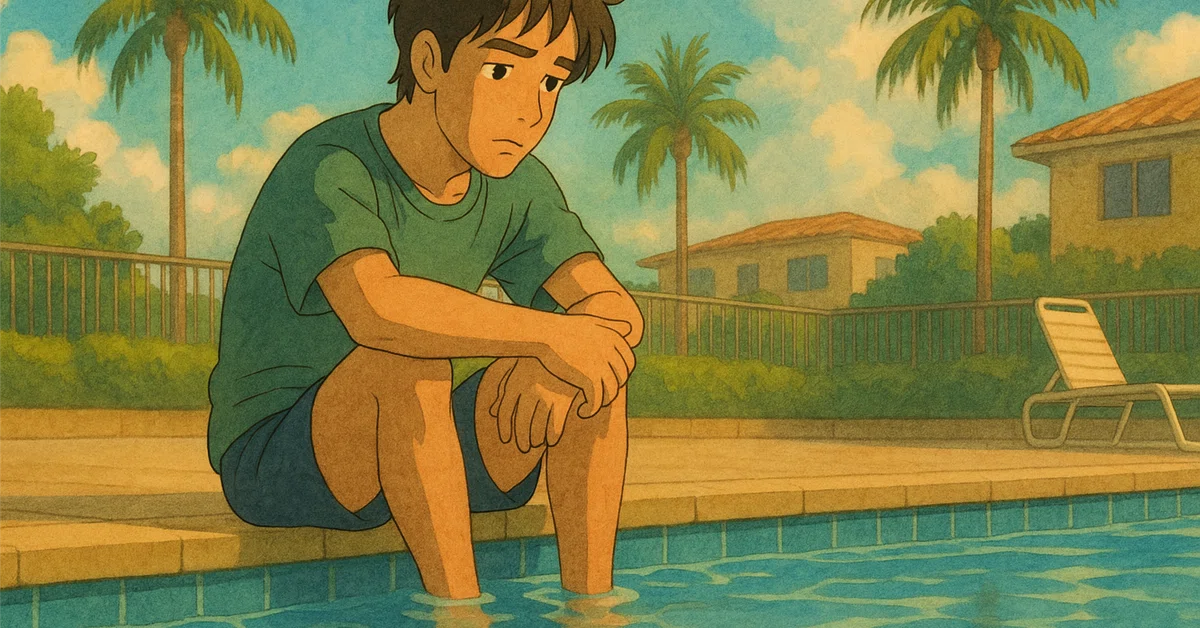
アメリカの光と影――プールで僕が見た本当の姿
いつもなら、僕はアメリカの素晴らしい面ばかりをご紹介している。自由、チャンス、ダイナミズム……そんなきらびやかな言葉たちで、この国を語ることに慣れている。
でも、今日は少し趣向を変えてみようと思う。
アメリカという国に、いまもなお根強く残る「影」の部分――つまり、人種差別について、僕自身の体験を交えてお話ししたい。
アパルトヘイトとアメリカ
「アパルトヘイト」という言葉を聞いたことがあるだろうか?
南アフリカ共和国がかつて採用していた、人種隔離政策のことだ。白人と非白人を徹底的に分け、非白人に不利な扱いをする社会構造。それは遠いアフリカの過去の話のように思えるかもしれない。
しかし、アメリカにもその影は色濃く残っている。
一般的には「アメリカの人種差別はなくなった」と言われる。でも、それは表面的な話だ。
心の奥底には、未だにくすぶるものがある。根っこの部分で、差別意識が息づいているのだ。
なぜそんなことが続くのか。
ひとつの説がある。
アングロサクソン、つまりヨーロッパ系白人たちは、もともと狩猟民族だったという説だ。常に獲物を求め、移動し、標的を定め、狩る。
その本能が、形を変えて現代にも引き継がれている。標的を探しては攻撃する――その対象が、有色人種に向けられているのだと。
もちろん、すべての白人がそうだとは言わない。でも、僕はあのとき、それを肌で感じたのだ。
ロサンゼルスの高級コンドミニアムで
僕には、アメリカに長く住む古い友人がいる。ロサンゼルスの高級コンドミニアムに住む彼は、ユダヤ系アメリカ人で、ある会社の副社長をしている。
僕が渡米するときは、いつも「うちに泊まれよ」と言ってくれる。なんと僕専用のゲストルームまで用意してくれているのだ。友情に感謝しつつ、僕もいつも甘えさせてもらっていた。
ある夏の日、ロサンゼルスの太陽が容赦なく照りつける午後。
「せっかくだし、泳ぎに行こう」と思い立ち、コンドミニアムに併設されている専用プールへ向かった。
誰もいないプールサイド。静かに体を水で濡らし、僕はざぶんとプールに飛び込んだ。
水中でふわりと身体を伸ばし、気持ちよく水面へと顔を出す。
その瞬間だった。
プールにいた他の人たちが、ざわざわと動き出したのだ。
バシャバシャと水音を立てて、次々とプールから上がっていく。
「あれ? なんだろう?」
僕は首をかしげた。
何か迷惑をかけたか?
でも、思い当たる節はない。ただ泳ぎに来ただけだ。
そんな僕の耳に、はっきりと飛び込んできた言葉。
「COLORED!」
色つきめ――。
呆然とした。
要は、僕がプールに入ったことで「同じ水に入ると色がうつる」とでも思ったのだろう。
僕は日本人、つまり黄色人種だ。肌は多少日焼けしていたが、彼らからすれば「有色人種」に見えたのだ。
怒りよりも、悲しみが先に来た。
ロサンゼルスでも、差別は生きている
ロサンゼルスといえば、多民族、多文化が共存する都市。
カリフォルニア州自体、アメリカの中でも比較的リベラルで、人種差別が少ないイメージを持っていた。
だからこそ、余計にショックだった。
「まさか、こんな場所で……」
不機嫌になった自分を感じながら、早々にプールを後にした。
タオルで体を拭きながら、ため息が止まらなかった。
コンドミニアムに戻ると、友人がソファで本を読んでいた。
「どうした?」
彼の問いに、僕はさっきの出来事をありのまま話した。
すると彼は、きっぱりと言った。
「うちのコンドの住民に、そんなこと言うやつはいないよ」
少しムキになっているようにも見えた。
僕は静かに反論した。
「でもさ、僕は有色人種だよ。日本人は黄色人種なんだよ」
彼は、しばらく黙った後、笑いながら言った。
「おまえのは、日焼けだよ。カラードじゃない」
彼らにとっての「色」とは何か
そのとき、僕は気づいた。
彼の中にも、無意識のうちに線引きがあるのだ。
「白」と「黒」、「白」と「色つき」、その間にある微妙なグラデーションを認めたくない、あるいは意識したくない心理。
彼に悪気はない。
むしろ、僕を守ろうとしたのだろう。
だけど、それこそが根深い問題だった。
「表面上はフレンドリーでも、本音の部分で区別がある」
それが、僕がアメリカで初めて直面した、見えない壁だった。
差別は、無くなったわけじゃない
アメリカでは、確かに多くの差別撤廃運動があり、法律も整備された。
黒人差別、アジア人差別、ヒスパニック差別、様々な歴史がある。
でも、人の心に根付いた意識は、法律では簡単に変えられない。
「俺たちは平等だ」と叫びながら、無意識のうちに誰かを線引きしている。
それが、アメリカという国の、いまも続くリアルな姿なのだと思う。
それでも、僕はアメリカを嫌いになれない
こんな経験をしても、僕はアメリカを嫌いにはなれない。
なぜなら、この国には、こうした現実を変えようとする人たちもまた、確かに存在するからだ。
「違いを受け入れることは、時間がかかる。でも、必ず変われる」と信じて努力している人たちがいる。
そして、そんな人たちとの出会いが、僕を何度も救ってきた。
差別は確かにある。
でも、それを乗り越えようとする希望も、同じくらい強く、ここには存在している。
だから、僕はまたアメリカへ行くだろう。
そして、こうしてまた、新しい現実と向き合いながら、少しずつ前に進んでいくのだ








