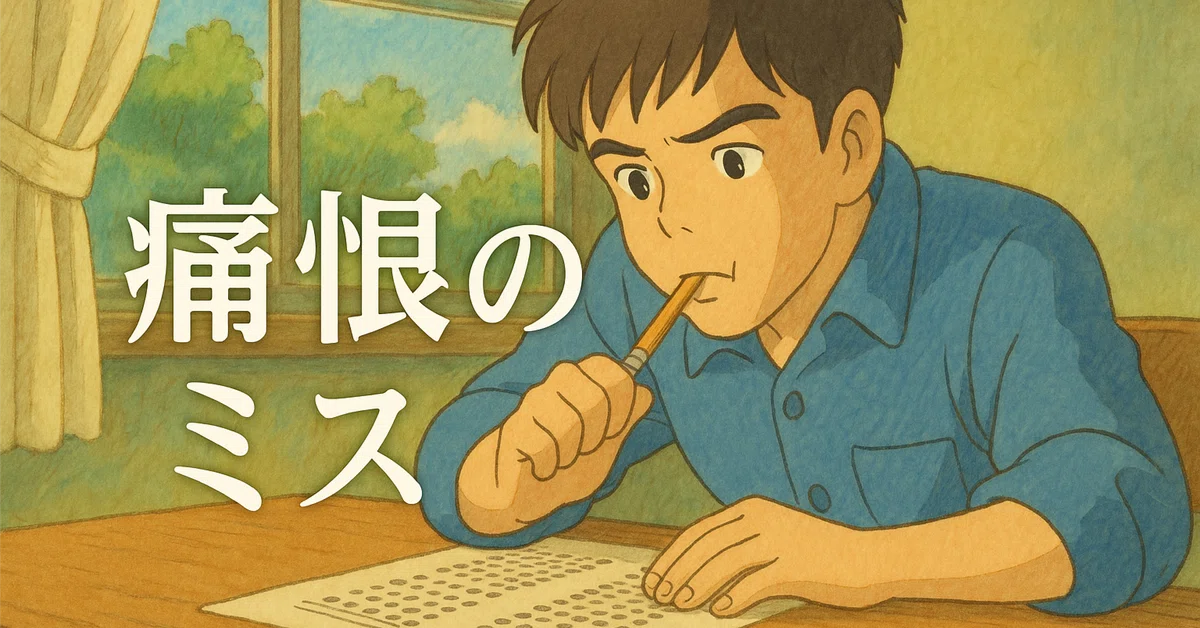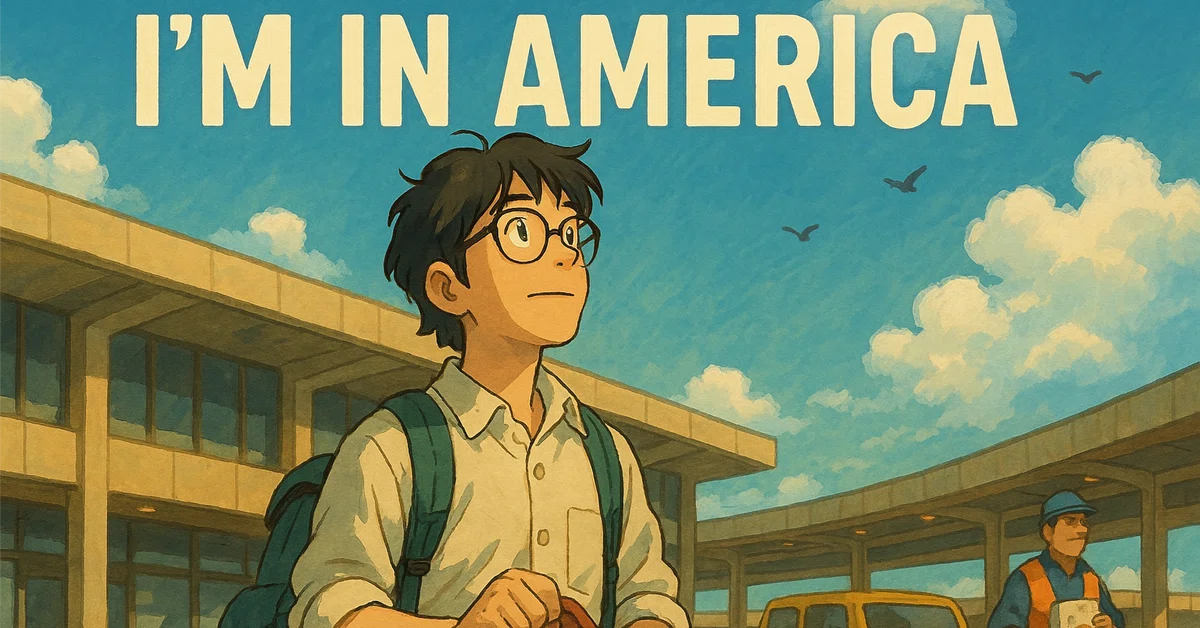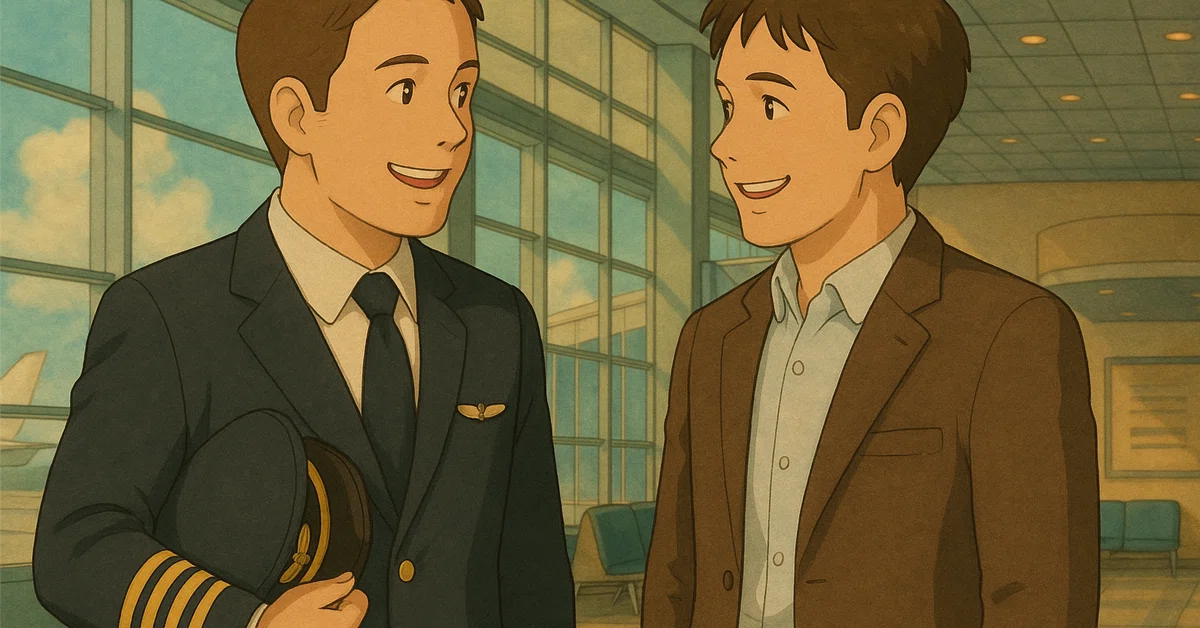アメリカで教わった、空からのエンタメ精神
※この記事は、筆者がアメリカ滞在中に体験した”空飛ぶサービス”について語る実話エッセイです。
アメリカに住むようになってしばらく経ったある日、僕は軽飛行機でのフライトを趣味とするようになっていた。週末になると、カリフォルニア北部を中心に各地の小さな飛行場を巡る日々。ベイエリア周辺の空港はほとんど行き尽くした頃だった。
そんなある晩、気の置けない友人たちと食事をしていたときのことだ。ふとした拍子に誰かが言った。「ラスベガス、飛んで行ってみたいよな」
当然、それはエアラインの話ではない。僕たちは自分たちの手で操縦桿を握り、500マイル先のネバダ州・ラスベガスまでの夜間飛行に挑戦しようというのだ。
「せっかくなら夜景を見ようじゃないか」
そんな話で盛り上がり、日程が決まると、胸の高鳴りはもう止められなかった。
ラスベガスを目指して
出発の日は雲一つない快晴。風も穏やかで、まさに飛行日和だった。
準備を終えてベイエリアの小さな飛行場を離陸。西の空に沈む夕陽を背に、僕たちは一路、東の空へ向かって飛び立った。地上がだんだんと闇に沈んでいくなか、僕の操る機体は高度を保ち、順調に進んでいく。
機内には、プロペラの唸りと、無線を通じて聞こえる航空無線のやり取りだけが響いていた。目的地のラスベガスまではおよそ2時間半。途中、ネバダ州に差しかかると、周囲は一気に真っ暗な砂漠へと変わっていく。
外の景色はほとんど何も見えない。頼りになるのは計器と地図、そして自分の経験のみ。
闇の先に待つ輝き
やがて、遠くに黒々とした山影が浮かび上がってきた。
その向こう側に、あのラスベガスがあるはずだ。
管制塔との交信が始まり、高度の変更とコースの指示が入る。指示に従い、山の上空を越えるのかと思いきや、どうやらそうではないようだ。
「そのまま高度を維持して、山沿いに進路をとってください」
ちょっと意外だった。
山を越えた方が最短なのに、なぜわざわざ迂回させるのだろう? と思いつつも指示に従う。
その数分後だった。
山を左に見る形で旋回したとき、突然――
目の前に、光の洪水が現れた。

それはラスベガスの夜景だった。
闇の中を進んできた僕たちの目に、いきなり飛び込んできたまばゆい光の海。
まさに、世界屈指のエンターテイメント・シティ。
誰かが「うわっ……」と息を飲んだ。僕も、心の中で叫んでいた。
「なんて演出だ……!」
サービス精神の正体
その後、空港へのアプローチでも管制官は親切に丁寧にナビゲーションしてくれた。
しかし、僕の心はもう着陸の瞬間にさえ釘付けではなかった。
「ひょっとして、さっきのルートは……わざと?」
最短距離で飛ばすなら、もっと早く山を越えていたはず。でも、あえて山を左に見ながら旋回させ、その切れ目から光の海を“突然見せる”ようなコースを取らせた。
それは、安全面だけでは説明のつかない、まるで舞台の幕が上がる瞬間のような劇的な演出だった。
僕は、こう思った。
「これこそ、アメリカ流のサービス精神なのではないか」
売らないけど、忘れられない
日本のサービスといえば、丁寧で正確で無駄のない対応というイメージがある。
一方アメリカでは、“体験”そのものがサービスとされる。
たとえば、ディズニーランドのキャストたちが、ただの誘導員ではなく、物語の登場人物としての役割を演じるように。
このラスベガス夜間飛行も、そうした「ストーリーの中に自分を招き入れる」ような演出だったのかもしれない。
誰かに何かを売ることがサービスじゃない。
記憶に残すこと、感動を与えること。
それが、彼らの考える“ホスピタリティ”なのだ。
あの夜の光は、今も忘れられない
今でも、あの夜のフライトを思い出すことがある。
ただの空港へのアプローチだったのに、心が震えるほどの感動があった。
「サービスとは、記憶に残すこと」
そんな教訓を、僕はあの夜、ラスベガスの上空で教わった気がする。
あれから何十年も経つけれど、あの山の切れ目から見えた光の波は、今も僕の記憶の中で煌めいている。